大学生の“考える力”を育てる第一歩〜流通科学大学の初年次教育改革における”問い”の価値〜
今年度、兵庫県にある私立大学・流通科学大学の初年次教育に、教育と探求社の「マイクエスチョン(My Question)」が導入されました。本記事では、初年次教育の設計を担った田邉先生に、その背景や導入のねらい、見えてきた変化についてお話を伺いました。

■ マイクエスチョン導入の経緯
これまでの初年次教育は、教員やゲスト講師の話を「聞く」ことが中心で、学生の活動が少なく、学びの実感が薄いという課題がありました。そこで、もっと学生が自ら動き、考え、対話できる場をつくりたいと考えました。
特に重視したのは、学ぶことの意味を自分で考えること。受け身ではなく、自分の内側から湧いてくる”問い”を出発点にすることで、学びは「自分ごと」になります。また、”問い”を通じて、自分が何に関心を持ち、何を学びたいのかを言語化できるようになると、それがやがて専門的な学びへの接続にもつながります。
こうした考えから、初年次教育の前期プログラムに「マイクエスチョン」を導入しました。学生が専門的な学びへと円滑につながっていけるように促すとともに、「学ぶ」ことの意味を主体的に考える力を育むことを目的としています。
■ 流通科学大学の初年次教育
本学では、初年次教育の一環として開講している「自己発見とキャリア開発」という科目において、今年度から「マイクエスチョン」を取り入れた講義を合計6コマ(9時間)で展開しました。
この講義では、「問いを見つけ、それを深めていく」ことを中心に据えて設計しています。問いを立てることで、普段は立ち止まって考えることのないようなことや、自分の中にある仮説に気づき、それを言語化できるようになります。さらに、問いの妥当性を検証したり、解決に向けて考えを深めたりするプロセスも自然と促されていきます。
こうした取り組みは、将来的に研究課題を設定するための前段階として非常に有効であり、ゼミや卒業研究へのスムーズな移行にもつながると考えています。
大学では、論文や研究計画書の作成が求められますが、その前段階として「なぜそれを調べたいのか」という本人の問いがなければ、学生の学びにつながらないと感じています。また、大学は正解を教える場所ではなく、正解や自分自身の納得解を探すスキルを育てる場であるべきだと考えています。学生自身が問いを立て、自らの学びを深めていく姿勢は、本学の初年次教育の理念とも重なっています。
【初年次教育とは】
大学に入学した1年生が、これからの学びに向けて土台を築くための教育です。専門的な知識を学ぶ前に、「学ぶとは何か」「自分は何に関心があるのか」「大学生活をどう過ごすか」といったことを、自ら考え、言葉にし、他者と共有する機会が用意されています。レポートの書き方や情報の扱い方など大学で学ぶスキルを身につけると同時に、自分の価値観や興味を掘り下げる時間でもあります。初年次教育は近年、各大学が独自に工夫を凝らしており、「学びのスタートダッシュ」としてますます重視されている領域です。
■ 実際に導入してみて
ポスター発表での様子や振り返りのポートフォリオを見ると、学生が「問いを立てる」ことの意味をしっかり捉えている様子が見て取れました。 学生からも「問いを見つけることが大事だと気づいた」という声があがってきており、実際に学ぶ姿勢が変わったと実感しています。
たとえば、学生のポートフォリオの記述からも、深い振り返りと充実感がうかがえました。中には、「これまでになかったタイプの講義だったが、自分で考え、言葉にするのが楽しかった」と記している学生もおり、主体的に学ぶことの面白さを感じていたようです。
講義後に、答えきれなかった問いを持ち帰った学生もいました。問いが日常に残り続けることで、その後も思考が継続していくその様子に、探究的な学びの芽生えを感じました。また、最初は正解っぽい問いを出していた学生も、だんだんと自分の違和感や関心から問いを立てるようになっていきました。問いを「育てる感覚」が少しずつ湧き出てきたのが印象的でした。そして、教授側にも変化がありました。学生に「問いを立てること」を求める中で、自分自身が研究の中でどのように問いを扱ってきたかを見直す機会となった、という声も聞かれました。
写真は、講義実施前に行われた研修の様子です。授業を担当する教授と、学生アシスタント(CA)に対して、教育と探求社の社員が「マイクエスチョン」の意図や活用方法について説明を行いました。現場に立つ教授やCAが、目的や背景を十分に理解することで、講義中の声かけや問いかけがより効果的になりました。

■ 今後に向けて
後期の初年次教育では、前期で育んだ「問いを立てる力」を生かし、アントレプレナーシップ教育につなげていく構想があります。学生が自分のありたい姿を見つけ、それに向かって努力できるように、キャリア開発にも接続させていきたいと考えています。
「マイクエスチョン」は、ただの探究スキルではなく、自身のアイデンティティと向き合う手段であり、大学で学ぶ意味を見つけるきっかけになるものです。今後も初年次教育の中で、「問い」の力を中心に据えた講義の設計を続けていきます。
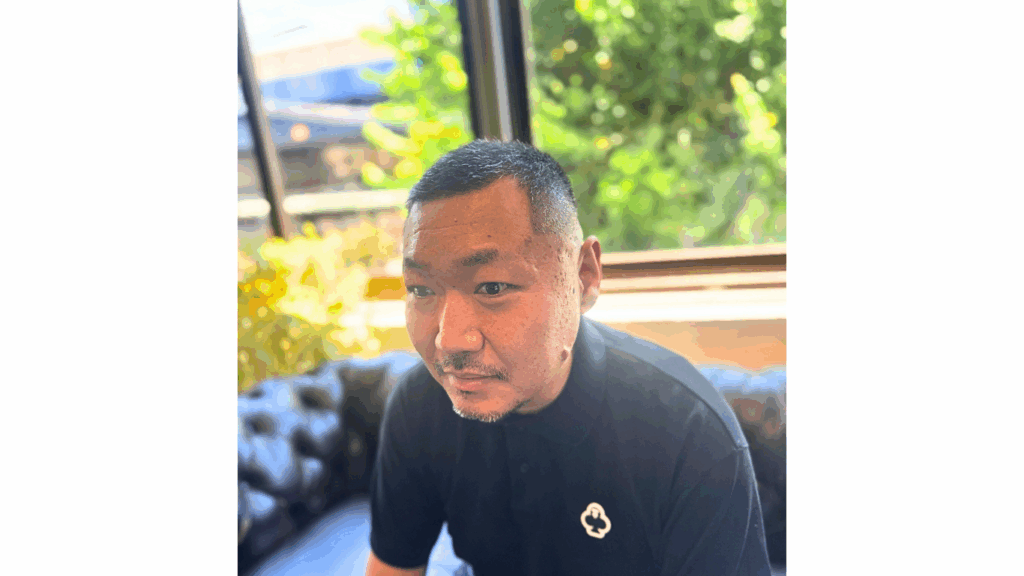
今回お話を伺った流通科学大学・田邉先生
■ 流通科学大学について
流通科学大学は、兵庫県神戸市にある私立大学で、1990年にダイエー創業者・中内㓛(なかうち・いさお)氏によって設立されました。建学の理念は、「流通を科学的に研究教育することを通じて、世界の平和に貢献し、真に豊かな社会の実現に貢献できる人材を育成する」。学生の主体性を重んじる教育方針のもと、経済・経営・商学・観光などの“実学”を重視したカリキュラムを展開しています。また「考える力」を育てる学習型教育への転換を進めており、学生の夢や関心を出発点とする独自プログラム「夢の種プロジェクト」を展開しています。
https://www.umds.ac.jp/