いわき市教育委員会が挑む探究教育――マイクエスチョン導入事例
教育と探求社は、2025年7月12日(土)、福島県いわき市教育委員会と連携し、中学生向け探究学習イベント「第2回 いわき志塾」を開催しました。「マイクエスチョン(MY QUESTION)」を活用し、生徒が自らの関心から問いを立て日常や地域と結びつけて考える、深い学びの一日となりました。
イベント後、いわき市教育委員会の浦島さんと森さんに、今回の取り組みの狙いや成果、今後への期待を伺いました。
▶ いわき志塾当日の様子はこちら:https://eduq.jp/news/iwakisijuku-report/

イベント内容の検討のため、いわき市教育委員会の方々に事前に体験いただいた様子

いわき市教育委員会 学校教育推進室 学校教育課 指導主事 森さん(左)浦島さん(右)
■ 探究って楽しい――生徒たちの変化や先生方の反応
イベントに参加した生徒たちは、絶妙な難しさの問いに対して、活発に、そして楽しそうに取り組んでいました。一見遊びにも見える活動の中で、真剣に考え、問いを深めていたその様子に、森さんは、「どんな教育関係者も、今回の子どもたちの姿を見れば、この学びの価値を感じられるはず」とおっしゃっていました。
中でも印象的だったのは、普段は物静かな生徒が自ら挙手して「家族ともやりたい」と発言した場面や、イベント後に平和教育の一環で長崎に派遣予定の生徒が「問いを立てるってこういうことなんだよ」と同行する仲間たちに今回の学びを共有していた姿です。こうした行動から、学びがその場限りではなく、日常へと広がっていき、新たな対話や発見を生むきっかけになる可能性が感じられました。
今回のイベントにおける学校現場からの直接的なフィードバックはまだまとめていませんが、参加したALTの先生からは「英語の授業で活用したい」との声が聞かれるなど、他の指導主事の先生方からも好評だったとのことです。
森さんと浦島さんは、「『問いを立てる』実践例が少ない今だからこそ、多くの先生に体験してもらう機会が必要」と語ります。
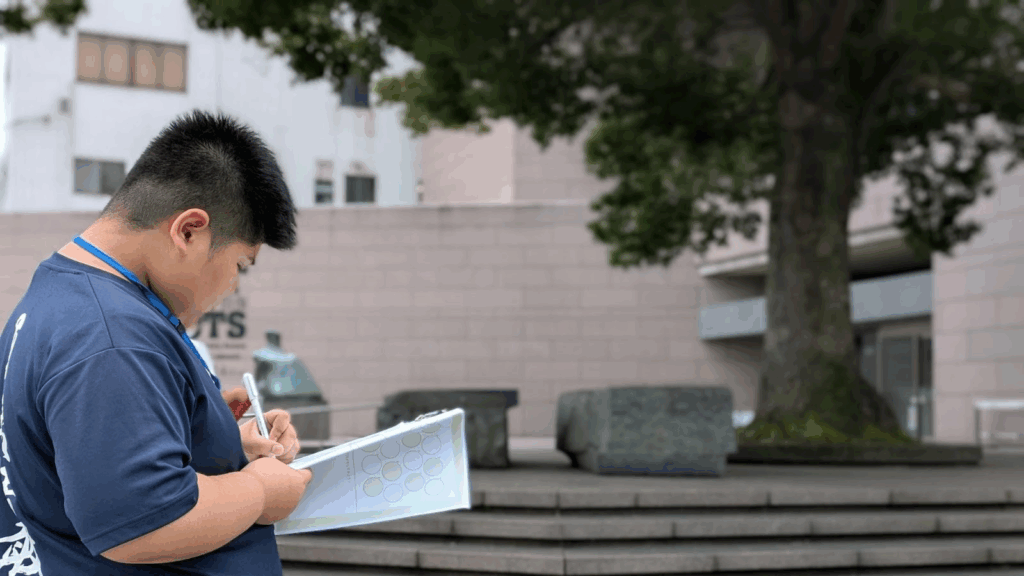
■ 実際に体験してみて――探究学習の意義と効果
当初、森さんは「問いを持たせる」授業の具体的な進め方に半信半疑だったと語ります。一方で浦島さんは、「マイクエスチョン」についてカードゲームのようなアクティビティという印象を持っていました。ですが、実際に体験してみて、その印象は大きく変わります。
「いつの間にか探究が始まっていた」。そう語る浦島さんは、楽しみながらも、自然と探究の世界に引き込まれていたという驚きがあったといいます。森さんもまた、日常の些細な疑問から自然に学びが深まるプロセスに感動し、「協働的な学び」と「個別最適な学び」が融合している点を高く評価しました。
そして、イベントを通して、見えてきた大きな意義は2つあったといいます。
1. 問いの多角化と思考の深化
カードを用いた問いづくりによって、生徒たちは多様な視点に触れ、自らの考えを広げていくことができます。森さんは「回数を重ねるごとに、異なる角度から考える意識が育つ」と期待を寄せています。
2. 協働と自己発掘の両立
グループでの議論と個々の探究が同時に進行するため、すべての生徒がフラットに参加し、それぞれの内なる問いと向き合います。浦島さんは、「文部科学省が提唱する学びのビジョン、『主体的・対話的で深い学び』(アクティブ・ラーニング)が、ここに具体化されている」と実感しています。
■ 地域を越えた学びの連携、そして先生自身の学びへ
森先生と教育と探求社の出会いは2023年。教育と探求社が発行する「クエストペーパー」を偶然手にする機会があり、そこに紹介されていた「探究学習の20年にわたる成果」や「クエストカップ」に目が留まり、知的分野における甲子園のような大会の存在に大きな可能性を感じたことで、「いわき志塾にぜひ取り入れたい」という思いが湧き、今回の連携につながりました。
▶ クエストペーパーとは(教育と探求社公式サイト):https://eduq.jp/for-school/quest/quest-paper/
いわき市は豊かな自然に囲まれ、学びの舞台としても魅力的な地域である一方で、限られた範囲での地域連携が中心でした。教育と探求社との協働によって、地理的な制約を越えて全国の教育機関や企業とつながる機会が生まれたといいます。
「これまでは“なぜ遠方から?”という声もあったが、今は“子どもたちのために”という視点で、全国と連携すべきだと考えている」と、森さん。さらに今後は、生徒だけでなく、教師向けの体験会や、教師と生徒が一緒に取り組む混合型の探究学習の場もつくっていきたいと話してくれました。
浦島さんも「教える側と教えられる側という立場を超えて、ともに問いに向き合う仲間になれる学びの場」として、現場の先生方自身が「問い」を実感し、探究学習の価値を体験することが、今後の広がりには欠かせないと考えています。
■ 最後に
子どもたちの未来に必要不可欠な力を育む探究学習の可能性を信じ、いわき市教育委員会は地域や外部との連携を通じて、新たな学びの地平を切り拓こうとしています。
「探究って楽しい」——生徒たちのこの実感が、未来を変える力になると、私たち教育と探求社は信じています。
今後もいわき市教育委員会と連携しながら、生徒の主体的な学びを支える取り組みを継続していきます。また、こうした先進的な教育のモデルを全国各地に広げ、自治体との協働によって、未来を担う若者たちの探究心と可能性を育んでまいります。